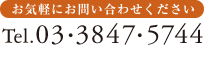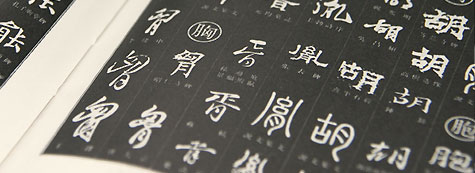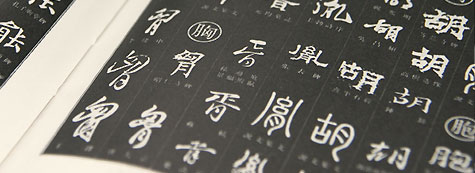
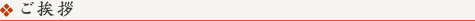
今こそ書を学ぶとき
日本人はかつて中国から漢字を取り入れ、また漢字“音”を借りて「ひらがな」をつくりました。
日本の文字文化は他のどの国よりも多様で奥深く繊細です。そして「書」は文字の文化と平行して育成されました。
スピードや利便性を求める昨今、手紙をはじめ文字をじっくり考えながら書くということは失われつつあります。
本校では漢字を書くと同時に日本の現代の詩や文も書きます。書を学ぶことの原点は日本語と改めて対峙するということです。
文字は正しく美しく書くと同時に漢字文化、日本語文化のすばらしさも学ぶことができます。今こそ書を学び墨に遊びましょう。
指導理念
本教室では漢字を書くと同時に日本語の現代の詩文も書きます。書を学ぶことの原点は文字を正しく書くと同時に、漢字文化日本語文化のすばらしさを学ぶことでもあると考えています。
基 礎
先人の優れた古典の法帖から多岐に渡る書法を学び、基礎を固めることを基本としています。法帖「九成宮」「蘭亭」「書譜」「風信帖」「曹全碑」他
創 作
作品創作の技術と理論を学び、個性を引き出し伸ばすことで優れた才能の発掘と書道美を目指しています。全国公募展で受賞者多数。「書道 五月女紫映社中展」では自由な発想で思い思いの作品を発表。
講 義
書の技術の向上と共に、心の感性の錬磨を求め、折りにふれ文学・歴史を交えながら授業を進めていきます。「万葉集を読む書く」「奥の細道を読む書く」「漢字発生の歴史」他

「書道 五月女紫映」
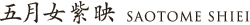
前・日本書道アカデミー会長
五月女玉環
※2014年より教室名と雅号を改めました
【書 歴】
- 1953年
- 東京に生まれる
小学校から「書道教室」に通いはじめ、中学、高校まで「高風会」に所属する - 1978年
- デザイン専門学校から染色の仕事を経て、書道学院に入門、大溪洗耳先生に師事
- 1981年
- 書道師範取得
- 1985年
- 書道師範養成学校の講師となる
- 1988年
- 公募「東京書作展」審査員となり、以降12年連続歴任
- 2001年
- 書道教室「書道 五月女紫映」を開校
- 2003年
- 公募「産経国際書会」審査会員となり以降現在まで歴任
- 2004年
- 日本台湾文化交流青少年スカラシップ(フジサンケイビジネスアイ主催)書道部門審査員となり、以降現在まで歴任
【現 在】
- 「書道 五月女紫映」主宰
- 「産経国際書会」常務理事・審査会員
- 「日本台湾文化交流青少年スカラシップ」書道部門審査員
【著 作】
「一から学ぶ漢字かなまじり文」 (日本習字普及協会)
【展覧会入賞履歴】
- 1981年
- 東京書作展にて優秀賞受賞
- 1982年
- 東京書作展にて優秀賞受賞
- 1983年
- 東京書作展にて名誉顧問・田邊古邨賞受賞
- 1984年
- 東京書作展にて内閣総理大臣賞受賞
【個展開催】
- 1986年
- 第1回個展 (有楽町マリオン・朝日ギャラリーにて)
- 1987年
- 第2回個展 (有楽町マリオン・朝日ギャラリーにて)
- 2001年
- 第3回個展 (有楽町マリオン・朝日ギャラリーにて)
- 2007年
- 第4回個展 (銀座・鳩居堂画廊)
- 2017年
- パリ個展 (エチエンヌ・ドウ・コーザン・ギャラリー (Galerie Etienne de Causans) )
【社中展開催】
2002年〜2020年まで全18回
(有楽町交通会館ギャラリー他)
【海外交流展出展】
- 2004年
- 「中華民国諸学会」「台湾淡江大学」と交流展(国立国父記念館にて)
- 2019年
- アブダビ展示会「ADIHEX」出展
【マスコミ関係報道一覧】
- テレビ
- テレビ東京「たけしの誰でもピカソ」 出演・作品揮毫
- 朝日ビール十六茶企画「大和撫子・和のお稽古会」 書道レッスンを担当
- NHK(BS2)「熱中時間〜忙中趣味あり〜」 文字と遊ぶ 俳優・松村雄基の書道
(松村雄基氏の書の師匠として出演) - 映 画
- 「失楽園」書道シーンの演技指導、作品提供
- 「武士の家計簿」書道所作指導
- 雑 誌
- 「週刊読売」墨の色に魅せられて 掲載
- 「女性自身」いつだって行動適齢期 掲載
他多数